
皆さん、こんにちは(こんばんは)、「大」(@oooohanamaru)」です。
今回は「MINOLTA MD ZOOM ROKKOR 35-70mm F3.5」をご紹介したいと思います。
ミノルタSRマウントのレンズになりますので、Nikonのカメラで使用するには、マウントアダプターを介して装着しています。
焦点距離が35〜70mmと、広角から中望遠まで幅広くカバーできる便利なレンズになります。
開放F値はF3.5 と、標準ズームレンズとして標準的な明るさですが、フルサイズ対応のレンズとしてはコストパフォーマンスに優れています。中古で手軽に手が出せる価格帯なのが嬉しいですね。
明るさが必要ないシチュエーションや日常使いには十分な性能を持ち、比較的お求めやすい価格で手に入るのが魅力です。
 嫁ちゃん
嫁ちゃんきた!またミノルタのレンズだね。
最近は「50mm」の単焦点レンズを収集してきたんだけど、ミノルタMDのズームレンズが欲しかったんだよね。
 嫁ちゃん
嫁ちゃんやっぱりMDは軽くていいね。
注)オールドレンズを購入される場合、現行の新品レンズとは違い、生産が終わった中古しかないこと、個体差があること、状態の程度もそれぞれなので、当たり外れがあるかもしれませんので、自己責任でよろしくお願いします。
この「MINOLTA MD ZOOM ROKKOR 35-70mm F3.5」は、ヤフオク等でレンズの状態の確認はできませんが、安価に売られているレンズですね。
私は、オールドレンズにあまりお金をかけたくないので、レンズフィルターも安いものを選んでいます。
はじめに
私は購入してから知ったのですが、「MINOLTA MD ZOOM ROKKOR 35-70mm F3.5」は3世代あるようで、このレンズは「初期型」のようです。
1978年発売のレンズで「ROKKOR」の文字がレンズ側面に刻されています。
こちらもミノルタSRマウントのズームレンズをレビューしていますので、良かったら読んでみてください。

使用するカメラ、マウントアダプター
今回は、フルサイズミラーレス「Nikon Zf」にマウントアダプターを使って、このレンズを試してみたいと思います。
Nikon Z f は、センサーサイズがフルサイズになりますので、「MINOLTA MD ZOOM ROKKOR 35-70mm F3.5」のレンズの焦点距離「35-70mm」のまま使用することができます。
Nikon Z fc の場合はセンサーサイズが、APS-C ですので、35mm版換算で、42-105mm相当の焦点距離で使用できます。
ちなみに、Zfcに装着するとこんな感じ。
どうでしょうか?案外、見た目にもしっくりきました。
少し、レンズの方が大きいかなという感じですね。

今回紹介するレンズの紹介
改めまして、今回紹介するオールドレンズは、「MINOLTA MD ZOOM ROKKOR 35-70mm F3.5」になります。
オートフォーカスの純正レンズ1本分の価格で複数のオールドレンズが購入できる安価な製品ですが、その作りはしっかりとしています。
1978年に発売されたレンズですが、現在でも問題なく使用できる品質の高さは、さすが「MADE IN JAPAN」の証です!

レンズのカビやクモリの有無を完全に判断することはできませんでしたが、フォーカスリングと絞りリングの動作は滑らかで、外観も美しい状態でした。
これは価格を考えると妥当なトレードオフと言えます。
絞りリングには適度なクリック感があります。

カメラに付けた際に、それなりに重さを感じました。
重量は「約359g(実測)」になります。
ちなみに以前レビューした「TAMRON 35-70mm F3.5-4.5 CF MACRO BBAR MC ADAPTALL 2 09A」は「約393g(実測)」です。

レンズキャップはあまり高価なものは買わないので、特にメーカーなど気にならない方は、この 55mm のキャップで十分だと思います。
仕様
「MINOLTA MD ZOOM ROKKOR 35-70mm F3.5」の仕様

| 型式 | ミノルタSR(MC/MDマウント) |
|---|---|
| 焦点距離 | 35-70mm |
| レンズ構成 | 7群8枚 |
| 対応撮像画面 | フルサイズ |
| フォーカス | MF(マニュアルフォーカス) |
| 最短撮影距離 | 1m |
| 絞り羽根枚数 | 6枚 |
| 最大絞り | f/3.5 |
| 最小絞り | f/22 |
| フィルターサイズ | 55mm |
| 寸法 | Φ65 x 64mm(実測) |
| 質量 | 359g(実測) |
| 販売年月 | 1978年 |
| 販売時価格 | -円 |
「Nikon Z f」の仕様概要

| レンズマウント | ニコン Z マウント |
| 有効画素数 | 2450万画素(総画素数2528万画素) |
| センサーサイズ | フルサイズ/FXフォーマット |
| ISO感度 | 100〜64000 |
| 高速連続撮影 | 約30コマ/秒(ハイスピードフレームキャプチャー+(C30)時の撮影速度で、JPEG [L]、NORMALに固定。推奨カードの使用時) |
| 約14コマ/秒(JPEGで高速連続撮影(拡張)時の最大撮影速度 | |
| 動画撮影 | 4K UHD 60p |
| フルHD 1080/120p | |
| 寸法 | 約144 x 103 x 49mm |
| 質量 | 約710g |
| その他の機能 | Wi-Fi内蔵(IEEE802.11b/g/n/a/ac) |
| Bluetooth内蔵(Ver.5.0) | |
| タッチパネル | |
| バリアングル液晶 |
K&F Concept MD – NIK Z マウントアダプターの仕様

| 対応マウントレンズ | MINOLTA MDレンズ |
|---|---|
| 対応マウントカメラ | Nikon Z カメラボディ |
| サイズ | 約Φ68x34mm |
| 重量 | 137g |
| 材質 | 真鍮、アルミニウム合金 |
| カラー | ブラック |
ミノルタについて
ミノルタは1928年に設立された日本の光学機器メーカーで、当初の名称は「日独写真機商店」でした。後に「千代田光学精工株式会社」となり、1962年に「ミノルタカメラ株式会社」に改名されました。同社は、カメラやレンズ、複写機、プリンターなど幅広い製品を製造し、特にカメラの分野で世界的に著名となりました。1958年には、「ミノルタオートコード」が登場し、自動露出計を内蔵した中判二眼レフカメラとして高い評価を受けました。また、1977年には世界初のカメラ内蔵式ピクチャープリント機能を持つ35mm一眼レフカメラ「XDシリーズ」を発表し、業界に革新をもたらしました。
1985年には、画期的なオートフォーカス一眼レフ「ミノルタα-7000」を発売し、カメラ技術の新たな基準を確立しました。このカメラは、世界初となるボディ内蔵型オートフォーカス機能を持ち、その後のデジタルカメラ時代にも受け継がれる技術基盤を作りました。2003年にはコニカ株式会社と合併して「コニカミノルタホールディングス株式会社」となり、さらに2006年にはカメラおよび写真フィルムの事業から撤退し、複写機やプリンター、医療機器などの分野に集中しました。
現在でも、ミノルタ製のカメラやレンズは中古市場で根強い人気を誇り、その高品質と信頼性で多くのカメラ愛好者から支持されています。カメラ市場からは撤退しましたが、その技術と設計哲学は、多くの現代のカメラメーカーにも影響を与え続けています。ミノルタの歴史は、日本の光学技術の発展に大きく寄与し、その名は今もなお語り継がれています。
詳しくは以下のサイトで、コニカミノルタの沿革について知ることができます。

K&F Concept について

K&F Conceptは、写真および映像機器のアクセサリーを製造・販売する中国の企業です。2011年に設立され、本社は深セン市に所在します。比較的新しいブランドながら、高品質とコストパフォーマンスの高い製品を提供し、急速に市場での存在感を高めています。主な製品ラインアップにはカメラフィルター、三脚、レンズアダプター、カメラバッグなどがあります。
カメラフィルターでは、NDフィルター、CPLフィルター、UVフィルターなどがあり、高品質な光学ガラスと多層コーティング技術を用いることでクリアでシャープな画像表現を実現しています。三脚は軽量かつ頑丈で、カーボンファイバーやアルミニウムを使用し、持ち運びやすさと耐久性を兼ね備えています。レンズアダプターも精密な設計と製造が施され、高い装着精度と耐久性を誇ります。カメラバッグは機能性とデザイン性が両立し、プロフェッショナルな撮影現場でも活躍します。
K&F Conceptは品質管理に厳格なポリシーを持ち、製品の設計から製造、出荷までの全工程で高い基準を維持しています。また、顧客からのフィードバックを重視し、製品の改良や新商品の開発に反映しています。環境への配慮も取り入れており、エコフレンドリーな素材の使用や廃棄物のリサイクルなどに取り組んでいます。
その革新性とコストパフォーマンスの高さから、多くの写真および映像愛好者に支持されるブランドであり、今後もさらに成長が期待されます。
「K&F Concept 日本」サイトは以下のリンクからいけます。
使ってみた感想
まず感じたのは、カメラボディ(710g)+マウントアダプタ(137g)+レンズ(359g)の組み合わせで、かなりズッシリとした重量感があります。フルサイズミラーレスカメラとしては標準的な重さですが、長時間の撮影では考慮が必要かもしれません。
これにSmallRigのカメラグリップ(102g)が加わりました。グリップは安定した持ち心地を実現してくれますが、その分重量も増えることになります。
総重量は「1,308g」となります。これは「1kg」を超える重さで、デジタルカメラとしては決して軽くはありません。ただし、この重量感が安定した撮影をサポートしてくれる面もあります。
特に最近は「Nikon Z fc」(445g)にコンパクトな中華製レンズを使用していたため、この重量差を強く実感しました。
カメラボディとレンズが重くなると、安定性のためにグリップを追加したくなりますが、それがさらに重量を増やすというジレンマがあります。
総重量約1.3kgは確かに重めですが、この重さだからこそグリップがあると安心感が増します。
なお、使用するカメラボディやマウントアダプタの組み合わせによっては、より軽量に抑えることも可能です。
外観
装着した見た目はこんな感じです。
このレンズはカメラボディ側から「絞りリング」「ズームリング」「フォーカスリング」の順に並んでいます

絞りリングはクリック感があり、感触がいいです。
フォーカスリング、ズームリングはトルク感がちゃんとありましたが、若干軽い感じでした。

やはり、Z f には、こういったオールドレンズがマッチしますね。
Z f がオールドカメラ風デザインですが、やはり、この時代のレンズと比べると、今風ですね。
レンズフィルターや、キャップをつけるともう少しレンズが長くなってしまいますが、仕方ないですね。

使っているカバン、ストラップ
最近、私は「HAKUBA カメラバッグ Chululu レニュー フラップショルダーバッグM オリーブ」を使っています。

とても軽いバッグで、この記事で紹介しているカメラ(Zf)にレンズを装着した状態で収納できます。
私はこの他に、一緒にiPad miniも収納しています。



カメラストラップは、ネックストラップや、ショルダーストラップ、ハンドストラップなど、使い分けたいので、アンカーリンクスをストラップに装着して、気軽に交換できるようにしています。

自宅に帰ったら、ストラップを外し、また外出時に好みのストラップをつけるというような運用をしています。
Zf はバリアングル液晶になっており、液晶を開けた時にストラップがあると邪魔になることがあります。ハンドストラップなら、片側だけにストラップを取り付けるので、液晶の邪魔にならないところがいいですね。
試し撮り
「Nikon Zf」を購入した理由にもノスタルジーがありましたので、このレンズは私のイメージにぴったり合っていると思います。
このレンズの最短撮影距離は1mで、焦点距離70mmで撮影すると、下の写真のような写りになります。
接写には向いていないため、ピントを合わせる際は一歩下がる必要があります。
近接撮影ができないのは時に不便ですが、通常の撮影では1m以上離れて撮ることが多いので、アップ写真やテーブルフォトは少し引いた構図になります。
マグカップとは1mの距離がありますが、ズーム効果により被写体を近くに寄せて撮影できます。

ズームリングを回すと連動してフォーカスリングが回る仕組みとなっています。
焦点距離 70mmに合わせるとこれくらいの距離の写りになりました。

愛犬を撮ってみた
なんといっても、愛犬チワワの「そら君」を撮影することが、私が写真を続けている最大の理由と言えます。
マニュアルフォーカスの場合、動き回るペットにピントを合わせるのに手間取り、シャッターチャンスを逃してしまうことがあります。
特に室内の暗い環境では、十分なシャッタースピードを確保できないため、もう少し明るい開放値のレンズの方が適していると感じました。
ただし、下の写真程度の画質であれば、ISOを上げることで十分対応できるので、あまり神経質になる必要はないでしょう。
このレンズで撮影を重ねるうちに、自然とピント合わせが素早くできるようになってきます。最初の慣れない時期さえ乗り越えれば、スムーズに撮影できるようになると思います。

ピントが外れた写真が多くなりがちですが、撮影時は枚数を気にせず多めに撮影し、後でピンボケ写真をRAW現像の対象から除外すれば良いだけです。
最近のミラーレス一眼カメラには、マニュアルフォーカスでもフォーカスピーキング機能があり、ピントの位置が確認できるため、マニュアル操作を避ける必要はありません。
私は主にRAW形式で撮影し、Macで現像作業を行っています。
必要に応じて、カメラからiPhoneにデータを転送し、SNSに投稿することもあります。
露出調整やトリミングを行わない状態で、この程度の距離感での撮影が可能でした。

写真が暗めに見える方もいらっしゃるかもしれませんが、撮影時の状態をそのまま残したいという私のこだわりから、このような写真も採用しています。
最短撮影距離が近いレンズでは、カメラをペットに近づける必要があるため、警戒されてしまうことがあります。
今回の「そら君」の写真も、なかなか近寄ってきてくれなかったため、少し遠めの撮影となってしまいました。
一見すると迫力に欠ける平凡な写真に見えますが、RAW現像で露出調整やトリミングを施すことで、十分使える写真に仕上がります。
ただし、これは作品としての完成度よりも、記録としての価値を重視した選択かもしれません。








オールドレンズを手に取って、次はどんな写真が撮れるかなと思いを巡らせるのは、とても楽しいので、続けていけるいい趣味だなと思います。
風景を撮ってみた
定点観測ではないのですが、レンズを購入した際には、同じポイントで撮影することにしています。
「さて、どんな感じに写るかな?」と言う感じで、一番の楽しみな瞬間かもしれません。
いつもの田んぼの風景と、近隣を撮影してみました。
少し歪んでおりますが、広角側 35mmで撮ってみました。

こちらは、望遠側 70mm で撮ってみました。

私のセンスというか、技量というか、そういったものを試されるんだろうなという感じの写真。
無限遠での、シャープさはあまりないかなと思いました(私には技術的にレンズの無限遠の調整などができません)。
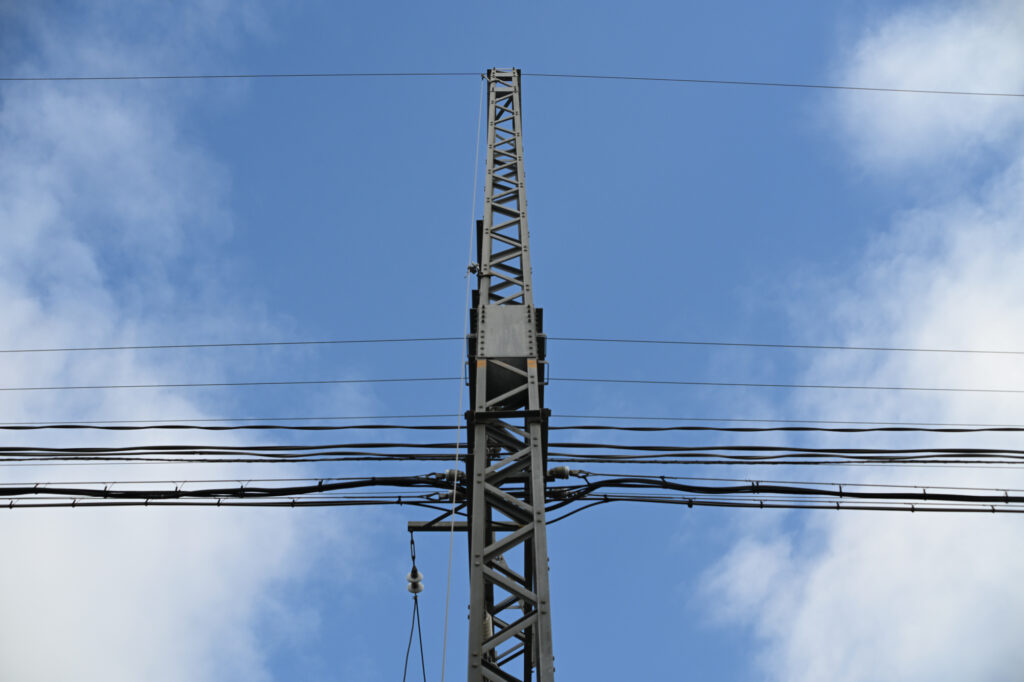


私は、この写真を見て、現行モデルのレンズか、オールドレンズかの違いが判断できません。
ちゃんと撮れてるし、問題ないかなといつも思い、なら、オールドレンズの方が価格が抑えられるからいいかなとか思ってしまします。
電車を撮ってみた
近鉄の列車を撮ることも定点にて行なっています。
ISOは分かりませんが、シャッタースピードは1/1000秒、絞りF8で撮影しています。
私は、鉄道関連について詳しくないのですが、列車は単純に被写体として好きなので撮っています。






好きな被写体を撮っている時はとても充実しています。
私にこれ以上の「伸びしろ」があるかどうか分かりませんが、もっといい写真が撮れるようになりたいです。
カスタムピクチャーコントロール
Z f に搭載されているピクチャーコントロールは「SD スタンダード」で、撮ることが多いのですが、今回は、カスタムピクチャーコントロールも使ってみました。
こちらのサイトで、カスタムピクチャーコントロールをダウンロードできますので、お気に入りのピクチャーコントロールを探されるのもいいと思います。
私は「Xpro2」というFUJIFILM風のピクチャーコントロールが気に入っています。
少しコントラストが強い傾向があるのかもしれません。
SNS等では、あまり暗い写真は好まれないかもしれないので、少し明るく撮ればいい感じになるのではないでしょうか。
RAW現像することが前提であれば、撮影時は好みのピクチャーコントロールを使って、後で変更することもできます。
Nikon Z f の撮影モード「B&W」でモノクロ撮影もよくしています。

使ってみた感想のまとめ

「MINOLTA MD ZOOM ROKKOR 35-70mm F3.5」を使ってみた感想です。
このレンズは1978年に販売されていたものですが、今となればクラシカルなデザインがとても魅力的です。
このレンズはヤフオクで手に入れましたが、市場にはたくさん出回っているようです。
値段もこなれていて、手軽な価格で手に入ることが嬉しいポイントになります。
重さは、359gと、私の主観では、意外と軽量でしっかりした作りのレンズだなという印象です。
操作自体も通常のズームレンズを扱うのと何ら変わりはありませんので、あとは被写体に集中するだけになります。
また、絞りリングはクリック感があり、正確に設定できるのも便利です。
デジタルカメラにもマウントアダプターを使って簡単に装着可能で、特にNikon Zfとの組み合わせは見た目のバランスが良く、デザイン的にもスタイリッシュにまとまります。
焦点距離が35-70mmの標準ズームレンズなので、風景やスナップ撮影に使いやすく、私の主目的でもある「そら君」の記録を残すという作業も楽しいものになっています。
絞りの最大開放F値が「3.5」と、それ程、明るいレンズではありませんが、先述しているようなペットの撮影なども行え、ズーム機能の利便性を考えると十分実用的な印象です
一方で、オールドレンズ特有の弱点もあります。
逆光に弱く、直射日光を受けるとフレアやゴーストが発生しやすいです。
ただ、これを個性として活かすことで独特な表現も楽しめます。
撮影時にはアングルに工夫が必要な場合もありますが、こうした特徴がオールドレンズの醍醐味ともいえるでしょう。
総合的に、「MINOLTA MD ZOOM ROKKOR 35-70mm F3.5」は、オールドレンズならではの味わいを堪能できる一本です。
現代の高性能レンズでは得られない魅力があり、写真撮影の楽しさを再発見させてくれます。オールドレンズ愛好家や、クラシカルなデザインを好む方にはぜひおすすめしたいレンズです。
良かった点、イマイチだった点

良かった点
- 価格がお手頃
- 意外とシャープに写ってくれる
- 絞りと、マニュアルフォーカス、ズーム(操作自体が楽しい体験になる)
- 懐かしいスタイルを楽しめる
イマイチだった点
- 開放F値が、F3.5とあまり明るくない
- 最短撮影距離 1m と被写体との距離が離れてしまう
- 少し重い(359g)
おわりに

標準的な広角から中望遠をカバーする焦点距離のレンズですが、私自身は特に50mmや35mmを使うことが多いため、この標準ズームレンズは両方の焦点距離に対応できる便利な一本でした。
被写界深度は浅すぎず、ピント合わせがしやすいのも魅力です。ピントの山を見つけるのに苦労することは少なく、一度コツをつかめばスムーズに撮影できます。使えば使うほど操作にも慣れてきたので、これからもっと練習していきたいと思います。
また、このレンズは中望遠の70mmとしても活用できるため、ポートレートやテーブルフォトなどのマクロ撮影にも十分対応可能です。
特に、Nikon Zfと組み合わせた際の見た目の相性が抜群で、ファッション性を重視した私にとって理想的でした。そもそも、オールドレンズを楽しみたいから「Nikon Zf」を選んだと言っても過言ではありません。
さらに、APS-Cセンサー搭載のZfcに装着すると、42-105mm相当の焦点距離として使用でき、使い勝手の良さが際立ちます。異なるカメラボディでも活用できる汎用性の高いレンズだと思います。
 嫁ちゃん
嫁ちゃん手軽にズームレンズを試してみるのにいいかもね。
お値段以上の性能を発揮してくれる印象だね。
レンズフィルターは 55mm を購入しました。
マウントアダプターは各マウント毎に販売されていますので、使うレンズとボディに合ったものを選んでください。
この記事がお役に立ちましたら幸いです。
では、また。
※本サイトの漫画やイラストはフィクションであり、実在の製品・団体・人物・地名とは関係ありません。
※本サイトに掲載する情報には充分に注意を払っておりますが、その内容について保証するものではありません。
※本サイトの使用ならびに閲覧によって生じたいかなる損害にも責任を負いかねます。











